子犬の排泄のケア
 子犬は生後20日頃まで自分で排泄(はいせつ=おしっこやうんちをすること)することができません。通常は母犬が尿道口(にょうどうこう)や肛門(こうもん)をなめて刺激することで排泄が促されます。しかし何らかの理由で母犬が排泄を促そうとしないときは飼い主が代行してあげます。
子犬は生後20日頃まで自分で排泄(はいせつ=おしっこやうんちをすること)することができません。通常は母犬が尿道口(にょうどうこう)や肛門(こうもん)をなめて刺激することで排泄が促されます。しかし何らかの理由で母犬が排泄を促そうとしないときは飼い主が代行してあげます。やり方は、授乳のたびに尿道口や肛門にオリーブオイルを塗り、指先で軽く刺激してあげます。指先をなるべく汚したくない場合はお湯で濡らした脱脂綿でかるく叩いたりこすったりしても結構です。 おしっこやうんちが出たらガーゼや脱脂綿できれいにふき取って清潔にします。
子犬のおしっこ補助
子犬の食事のケア
子犬は産まれてからの約1年間で、急速に成犬の体型まで成長します。つまり生まれてから最初の一年間の栄養状態が犬の成長にとって極めて重要ということです。 以下では生後1年間の食事で気をつけるべき点を挙げていきます。
授乳期:誕生~生後3週間
子犬が誕生してから、口唇反射が消え、乳歯が生え始めるまでの約3週間が授乳期です。特に新生子期(生後10日くらいまで)の子犬は、空腹かどうかに関わらず、とりあえずおなかがパンパンにふくらむまでお乳を飲み続けるという、強い生存本能に突き動かされて母親の乳房に吸い付きます。
自然授乳と人工授乳
 生まれてから約3週間は母犬の母乳が主な栄養源となります。基本的には母犬の本能的な授乳(じゅにゅう)に任せますが、母乳の出が悪いときや子犬の成長が思わしくないとき、あるいは食いしん坊の子犬にはじかれてなかなか思うように吸乳できないようなときは、飼い主が介在して授乳する場合もあります。
生まれてから約3週間は母犬の母乳が主な栄養源となります。基本的には母犬の本能的な授乳(じゅにゅう)に任せますが、母乳の出が悪いときや子犬の成長が思わしくないとき、あるいは食いしん坊の子犬にはじかれてなかなか思うように吸乳できないようなときは、飼い主が介在して授乳する場合もあります。子犬の成長の度合いを知るには、生まれてすぐにスケーラー(ばねばかり)で子犬の体重を計り、毎日同じ時間に体重計測を行います。それをグラフ化すると子犬の成長過程がすぐに分かります。10日目で体重が2倍/3週目で体重が3倍というのが一つの目安です。
兄弟姉妹がいる場合は、それぞれの成長度合いを比較すると栄養の行き届いていない子がすぐに分かりますので、全員の体重チェックを行いましょう。
飼い主の育児補助
 産んだ仔の数が少なすぎて母性本能が誘起されない、ホルモンバランスの変化で子犬を攻撃する、病気で乳が出ないなど、様々な理由により母犬が授乳できない状況がまれに生じます。その場合、飼い主が母犬の代わりになって授乳してあげる必要がありますが、子犬用の哺乳瓶(ほにゅうびん)と、万が一子犬が哺乳瓶での授乳を受け付けないときのために授乳専用スポイトを用意しておくと安心です。子犬の口元に吸い口やスポイトの先端をもっていくと、口唇反射によって自動的にミルクを吸い込んでくれます。
産んだ仔の数が少なすぎて母性本能が誘起されない、ホルモンバランスの変化で子犬を攻撃する、病気で乳が出ないなど、様々な理由により母犬が授乳できない状況がまれに生じます。その場合、飼い主が母犬の代わりになって授乳してあげる必要がありますが、子犬用の哺乳瓶(ほにゅうびん)と、万が一子犬が哺乳瓶での授乳を受け付けないときのために授乳専用スポイトを用意しておくと安心です。子犬の口元に吸い口やスポイトの先端をもっていくと、口唇反射によって自動的にミルクを吸い込んでくれます。
また新生子(生後10日くらいまでの子犬)は脂肪が薄く、体温調整がうまくできません。ペットヒーターを30度くらいに保ってあげると、低体温症を予防することができます。ただし、低温やけどを防ぐため、必ずタオルなどをあてがい、肌に直接触れないよう注意します。
 産んだ仔の数が少なすぎて母性本能が誘起されない、ホルモンバランスの変化で子犬を攻撃する、病気で乳が出ないなど、様々な理由により母犬が授乳できない状況がまれに生じます。その場合、飼い主が母犬の代わりになって授乳してあげる必要がありますが、子犬用の哺乳瓶(ほにゅうびん)と、万が一子犬が哺乳瓶での授乳を受け付けないときのために授乳専用スポイトを用意しておくと安心です。子犬の口元に吸い口やスポイトの先端をもっていくと、口唇反射によって自動的にミルクを吸い込んでくれます。
産んだ仔の数が少なすぎて母性本能が誘起されない、ホルモンバランスの変化で子犬を攻撃する、病気で乳が出ないなど、様々な理由により母犬が授乳できない状況がまれに生じます。その場合、飼い主が母犬の代わりになって授乳してあげる必要がありますが、子犬用の哺乳瓶(ほにゅうびん)と、万が一子犬が哺乳瓶での授乳を受け付けないときのために授乳専用スポイトを用意しておくと安心です。子犬の口元に吸い口やスポイトの先端をもっていくと、口唇反射によって自動的にミルクを吸い込んでくれます。また新生子(生後10日くらいまでの子犬)は脂肪が薄く、体温調整がうまくできません。ペットヒーターを30度くらいに保ってあげると、低体温症を予防することができます。ただし、低温やけどを防ぐため、必ずタオルなどをあてがい、肌に直接触れないよう注意します。
子犬に適したミルク
以下に示すのは、各種ミルクに含まれる栄養成分の対比、および標準的な授乳方法です。犬用粉ミルクとは構成成分が大きく異なる人間用の粉ミルク、および牛乳は与えないようにします。後者は、犬が牛乳に含まれる乳頭(ラクトース)を分解するラクターゼという酵素をもっておらず、与えると下痢を起こしてしまうためです。
各種ミルクの成分表(水分5%の時の比較)
| 成分(%) | 犬用粉ミルク | 犬の母乳 | 人の母乳 | 人用粉ミルク |
| 炭水化物 | 16.5 | 16.9 | 57.2 | 58.0 |
| タンパク質 | 34.0 | 33.8 | 11.3 | 12.6 |
| 脂質 | 39.0 | 38.8 | 25.8 | 22.3 |
犬の日齢とミルクの標準給与量・分割回数
| 犬の体型 | 生後1日~ | 生後6日~ | 生後11日~ | 生後16~20日 |
| 超小型犬 | 5g | 10g | 12.5g | 15g |
| 小型犬 | 12.5g | 15g | 17.5g | 17.5g |
| 中型犬 | 17.5g | 25g | 32.5g | 42.5g |
| 大型犬 | 20g | 35g | 50g | 65g |
| 超大型犬 | 25g | 47.5g | 60g | 77.5g |
| 分割回数 | 8回 | 6回 | 4回 | 4回 |
- 犬の体型分類
-
上記した犬の体型は以下で示す成犬時の体重で分類します。
- 超小型犬= 1.0~4.5kg
- 小型犬=4.5~13.5kg
- 中型犬=13.5~27.0kg
- 大型犬=27.0~46.0kg
- 超大型犬=46.0~90.0kg
母犬のお乳を促す方法
授乳期において母犬の母乳をスムーズに出そうとするなら、まずはゆったりした音楽などをかけ、犬がリラックスできる環境を整えるということが大事なようです。
うるさくていらいらした牧夫によって管理されている乳牛よりも、無口で穏やかな牧夫に管理されている乳牛の方が、泌乳量が多いという経験則から、牛をリラックスさせるためにクラシック音楽をかけている牧場があります。
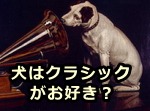 また、北アイルランドにあるクイーンズ大学の心理学者デボラ・ウェルズが、10頭の犬を対象にして行った実験では、犬はある特定の音楽に対して特定のリアクションを示すことが明らかになりました。犬にポピュラー音楽、クラシック、ヘビーメタルを聞かせたところ、ポピュラー音楽に対しては、まるで何も聞いていないかのように薄い反応を示し、ヘビーメタルに対しては、吠えるなど興奮気味の反応を示したとか。そんな中でクラシック音楽に対してだけは、寝そべったり吠えるのをやめたり、リラックスしているかのような反応を見せたといいます。
また、北アイルランドにあるクイーンズ大学の心理学者デボラ・ウェルズが、10頭の犬を対象にして行った実験では、犬はある特定の音楽に対して特定のリアクションを示すことが明らかになりました。犬にポピュラー音楽、クラシック、ヘビーメタルを聞かせたところ、ポピュラー音楽に対しては、まるで何も聞いていないかのように薄い反応を示し、ヘビーメタルに対しては、吠えるなど興奮気味の反応を示したとか。そんな中でクラシック音楽に対してだけは、寝そべったり吠えるのをやめたり、リラックスしているかのような反応を見せたといいます。
こうしたデータから考えると、母犬の初乳(しょにゅう)をスムーズに出そうとするなら、まずは見知らぬ人を人払いしたり、穏やかなクラシック音楽を掛けるなどして、なるべく犬をリラックスさせる環境を整えることが重要なようです。 また、お乳の出が悪いときは、飼い主がどれか一つの乳房や乳腺を優しくもむことで、射乳を促進できることもあります。子猫がよく見せるミルクトレッドというマッサージが有名ですが、一つの乳腺が刺激を受けると、なぜか全ての乳房で射乳が起こります。これは平均して5対10個ある乳腺が全てリンパ管でつながっているために起こる現象かもしれません。逆に、乳ガンにかかってしまったときは、患部のみならず全ての乳腺を切除しなければならないのも同じ理由です。
うるさくていらいらした牧夫によって管理されている乳牛よりも、無口で穏やかな牧夫に管理されている乳牛の方が、泌乳量が多いという経験則から、牛をリラックスさせるためにクラシック音楽をかけている牧場があります。
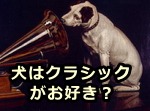 また、北アイルランドにあるクイーンズ大学の心理学者デボラ・ウェルズが、10頭の犬を対象にして行った実験では、犬はある特定の音楽に対して特定のリアクションを示すことが明らかになりました。犬にポピュラー音楽、クラシック、ヘビーメタルを聞かせたところ、ポピュラー音楽に対しては、まるで何も聞いていないかのように薄い反応を示し、ヘビーメタルに対しては、吠えるなど興奮気味の反応を示したとか。そんな中でクラシック音楽に対してだけは、寝そべったり吠えるのをやめたり、リラックスしているかのような反応を見せたといいます。
また、北アイルランドにあるクイーンズ大学の心理学者デボラ・ウェルズが、10頭の犬を対象にして行った実験では、犬はある特定の音楽に対して特定のリアクションを示すことが明らかになりました。犬にポピュラー音楽、クラシック、ヘビーメタルを聞かせたところ、ポピュラー音楽に対しては、まるで何も聞いていないかのように薄い反応を示し、ヘビーメタルに対しては、吠えるなど興奮気味の反応を示したとか。そんな中でクラシック音楽に対してだけは、寝そべったり吠えるのをやめたり、リラックスしているかのような反応を見せたといいます。こうしたデータから考えると、母犬の初乳(しょにゅう)をスムーズに出そうとするなら、まずは見知らぬ人を人払いしたり、穏やかなクラシック音楽を掛けるなどして、なるべく犬をリラックスさせる環境を整えることが重要なようです。 また、お乳の出が悪いときは、飼い主がどれか一つの乳房や乳腺を優しくもむことで、射乳を促進できることもあります。子猫がよく見せるミルクトレッドというマッサージが有名ですが、一つの乳腺が刺激を受けると、なぜか全ての乳房で射乳が起こります。これは平均して5対10個ある乳腺が全てリンパ管でつながっているために起こる現象かもしれません。逆に、乳ガンにかかってしまったときは、患部のみならず全ての乳腺を切除しなければならないのも同じ理由です。
- 初乳
- 初乳(しょにゅう)とは分娩後1週間~10日くらいまで分泌される乳汁で、その後に分泌される常乳(じょうにゅう)とは区別されます。固形分、タンパク質、脂肪、灰分が多く、乳糖が少ないこと、また免疫力を高める抗体(IgG、IgA、IgM)や、各種の成長因子(IGF、EGF、NGF)が多く含まれることを最大の特徴としています。
ですから初乳を飲んだ子犬は、飲んでいない子犬に比べ、母犬からの移行免疫(約90%)を受けている分、病気に対する免疫力が強くなるというわけです。
離乳食への移行期:生後3週目
 生後3週頃から口に当たったものを自動的に吸う「口唇反射」(こうしんはんしゃ)が消え、乳歯(にゅうし)が生え始めます。乳首に歯があたって痛いので母犬が授乳を拒み、自然と乳離れできることが多いようです。この頃から柔らかい離乳食(りにゅうしょく)を食事に混ぜるようにしましょう。離乳食とは乳歯でも噛み砕ける程度の柔らかい食事のことを言い、野生の犬においては、母犬が吐き戻した半消化状態のものがこれに相当します。
生後3週頃から口に当たったものを自動的に吸う「口唇反射」(こうしんはんしゃ)が消え、乳歯(にゅうし)が生え始めます。乳首に歯があたって痛いので母犬が授乳を拒み、自然と乳離れできることが多いようです。この頃から柔らかい離乳食(りにゅうしょく)を食事に混ぜるようにしましょう。離乳食とは乳歯でも噛み砕ける程度の柔らかい食事のことを言い、野生の犬においては、母犬が吐き戻した半消化状態のものがこれに相当します。いきなり母乳やミルクから離乳食に移すのではなく、ミルクと離乳食を半分ずつ与えるようにすると移行がうまくいきます。ドライフードを水や犬用ミルクでふやかしたものでも作れますが、近年は離乳食用のペットフードも市販されていますので、こうしたものも利用するようにします。
離乳食への移行目安
| 犬の体型 | 母乳・粉ミルク | 離乳食 |
| 超小型犬 | 2.5g | 体重の10~15% |
| 小型犬 | 5g | 体重の10~15% |
| 中型犬 | 12.5g | 体重の10~15% |
| 大型犬 | 15g | 体重の10~15% |
| 超大型犬 | 17.5g | 体重の10~15% |
| 分割回数 | 4回に分けて | |
- 犬の体型分類
-
上記した犬の体型は以下で示す成犬時の体重で分類します。
- 超小型犬= 1.0~4.5kg
- 小型犬=4.5~13.5kg
- 中型犬=13.5~27.0kg
- 大型犬=27.0~46.0kg
- 超大型犬=46.0~90.0kg
離乳食期:生後4週~生後8週
生後4週~8週まででほぼ乳歯が生えそろいます。この頃には乳離れして離乳食に切り替えます。犬は急速に成長しますので、体重の割にはかなりのエネルギー量を必要とするのがポイントです。以下に必要カロリー数の目安を載せますので参考にしてください。なお犬の成長速度は犬種や性別によって微妙に異なります。標準的な成長曲線に関しては、2017年にイギリス・リバプール大学の調査チームが目安となるものを公開していますので、以下のページをご参照ください。
犬の成長速度と必要カロリー数の関係
| 日齢 | 必要kcal/kg | 必要kcal/日 |
| 30 | 242 | 322 |
| 60 | 185 | 515 |
| 90 | 157 | 733 |
| 120 | 137 | 855 |
| 150 | 122 | 936 |
| 180 | 110 | 955 |
| 210 | 100 | 942 |
| 240 | 90 | 885 |
| 270 | 82 | 814 |
| 300 | 74 | 742 |
成犬移行期:生後8週以降
乳歯も生えそろい、いよいよやや固めの成犬食に移行します。必要カロリー数は上記表を参考にしてください。
生後2~5ヶ月(生後8週~20週)までの間に食に対する嗜好(しこう=好き嫌いのこと)が決定すると言われています。安易に人間の食事を与えないように注意しましょう。
また生後4~7ヶ月は歯牙脱換期(しがだっかんき)といって、早くも乳歯が永久歯に生え変わる時期です。この時期に柔らかいものばかり食べているとあごの骨が発達せず歯並びが悪くなったりしますのでなるべく固いものを食べさせたりかじらせたりしましょう。
下記表を目安にして成犬の食習慣に徐々に近づけていきます。
生後2~5ヶ月(生後8週~20週)までの間に食に対する嗜好(しこう=好き嫌いのこと)が決定すると言われています。安易に人間の食事を与えないように注意しましょう。
また生後4~7ヶ月は歯牙脱換期(しがだっかんき)といって、早くも乳歯が永久歯に生え変わる時期です。この時期に柔らかいものばかり食べているとあごの骨が発達せず歯並びが悪くなったりしますのでなるべく固いものを食べさせたりかじらせたりしましょう。
下記表を目安にして成犬の食習慣に徐々に近づけていきます。
犬に餌を与えるタイミングと分量の目安
| 給餌時間 | 午前7時頃 | 正午頃 | 午後5時頃 | 午後10時頃 |
| ~3ヶ月 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| 3~6ヶ月 | 普通 | 少なめ | 普通 | 少なめ |
| 6~12ヶ月 | 普通 | × | 少なめ | × |
| 12ヶ月~ | 適宜 | × | 少なめ | × |
補足説明
基本的には朝食をメインの食事とし、12ヶ月を過ぎるまでは成長期なので餌の量は多めにします。12ヶ月を過ぎた犬は1日1回の食事でも構いませんが、急に量を減らすのではなく、 1~2週間かけて徐々に餌の量を減らすように工夫してください。過剰な間食(おやつ)は肥満と生活習慣病の原因になりますので、 飼い主が責任もって監督管理します。また常に清潔で衛生的な水が飲めるようにしておいて下さい。
子犬の社会化期の育て方
犬には社会化期(しゃかいかき)というものがあります。これは兄弟犬を始めとする他の犬や、猫や兎など他の動物、 そして何より人間に対する警戒心をなくし、仲良く生活していくために必要な極めて重要な時期です。およそ生後2~12週の期間を言います。以下では概略を示しますが、より詳しくは 子犬の社会化期をご参照ください。
生後2~3週
 生後2~3週になると、子犬のまぶたが開いて目が見えるようになり、外耳道(がいじどう=鼓膜と外界とをつなぐ管)が開いて音が聞こえるようになります。また生後2週目には前足の触覚(しょっかく)が生まれ、生後3週目には後ろ足の触覚も生まれて立ち上がることができるようになります。つまりこの時期には5感を通じて外界から膨大な量の情報が入ってきて、それにあわせて脳も急速に成長するのです。
生後2~3週になると、子犬のまぶたが開いて目が見えるようになり、外耳道(がいじどう=鼓膜と外界とをつなぐ管)が開いて音が聞こえるようになります。また生後2週目には前足の触覚(しょっかく)が生まれ、生後3週目には後ろ足の触覚も生まれて立ち上がることができるようになります。つまりこの時期には5感を通じて外界から膨大な量の情報が入ってきて、それにあわせて脳も急速に成長するのです。この時期は主として兄弟犬、姉妹犬とたくさん遊ばせることが重要となります。この遊びやじゃれあいがないと、成犬になってから正常な交尾を行うことができないとも言われています。
生後3~7週
 この時期は人間を始め、その後の生活で子犬が密接に関わりあう動物と積極的に触れ合わせることが重要となります。この時期に他の動物と接触がないと、成犬になってから警戒心の強い犬に育ち、極端に臆病だったり逆に極端に攻撃的な性向を示すようになるという研究もあります。
この時期は人間を始め、その後の生活で子犬が密接に関わりあう動物と積極的に触れ合わせることが重要となります。この時期に他の動物と接触がないと、成犬になってから警戒心の強い犬に育ち、極端に臆病だったり逆に極端に攻撃的な性向を示すようになるという研究もあります。遊びやじゃれあいは子犬の筋力を養うと同時に、まだ未発達なバランス感覚(具体的には内耳の中の前庭器官)を刺激して訓練してくれますので非常に重要です。また取っ組み合いやかじりあいの中でコミュニケーション能力を身に付けていきます。
生後7~12週
 引き続き他の犬、他の動物、そして人間など色々な接触が重要となる期間です。犬の脳は生後12週までに急速に成長します。脳が完成してから他の動物に接触させてもなかなか受け入れませんが、脳が成長段階にあるときに他の動物と接触させると、柔軟に受け止めて警戒心も少なく友好関係を築きやすい性格に育ちます。
引き続き他の犬、他の動物、そして人間など色々な接触が重要となる期間です。犬の脳は生後12週までに急速に成長します。脳が完成してから他の動物に接触させてもなかなか受け入れませんが、脳が成長段階にあるときに他の動物と接触させると、柔軟に受け止めて警戒心も少なく友好関係を築きやすい性格に育ちます。この現象を理解するには人間の言語能力を思い浮かべると良いでしょう。一度日本語を覚えて母国語としてしまうと、後から英語を学ぶのに非常に苦労します。しかし子供の頃から日本語と英語を均等に使っていると、脳が両方の言語に対応していわゆるバイリンガルになります。重要なのは脳が発達段階にあるときに与えた情報は記憶されやすく、そして消えにくいということ、また逆に脳が完成してから与えた情報は記憶されにくく、そして消えやすいという点です。
脳が柔軟な「社会化期」に他の動物と友好な関係を築いておくと、成犬になってもその記憶が残り、他の動物に対して人なつこくて優しい態度を示すようになるのです。
子犬の社会化期と販売時期
 ペットショップなどで「生後1ヶ月程ではないか?」と思えるような非常に幼い子犬が売られていることもあります。しかし上記「社会化期」の重要性を理解した上でこの販売方法を考えると、今まで見えていなかった側面が見えてくるはずです。
ペットショップなどで「生後1ヶ月程ではないか?」と思えるような非常に幼い子犬が売られていることもあります。しかし上記「社会化期」の重要性を理解した上でこの販売方法を考えると、今まで見えていなかった側面が見えてくるはずです。売り手からすると生後45日までの子犬は見た目が非常にかわいく、すぐに売り手が見つかるので商売上便利でしょう。買い手からすると、子犬の性格を形成する上で最も重要な時期の多くをケージの中で過ごした子犬を買うことになります。つまり性格的に何らかの問題を抱えた子犬を飼ってしまう可能性があるということです。
ペットショップやブリーダーなどから子犬を飼う際は、先方がこの「社会化期」をどのように扱っているかが売り手のよしあしの判断材料になります。子犬の見た目や自分の利益を優先して、子犬の性格やその子犬を育てる飼い主のことなどを放置するようなスタンスの売り手は少なくとも見分けることができるのではないでしょうか。
子犬の引渡し時期
2012年8月、ブリーダーから売業者に対する子犬の引き渡し時期が、従来よりも遅い「生後56日」に移行するという案が成立しました。こうした立案の背景には、子犬たちがあまりにも早い時期にケージの中に囚われの身となり、社交性や優しさといったペットとして重要な性格形成がなされず、結果としてペットの遺棄・殺処分という社会問題につながっている、という考察があります。


